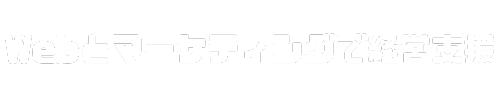「もっと知ってもらうには?」と焦るより、まずは目の前の1人を徹底的に理解してみませんか?
ニーズ・ウォンツ・インサイトの違いをつかみ、顧客の声から見える事業のヒントを拾う。
地方での商売こそ、信頼の積み重ねが売上の土台になります。
本記事のポイント
- ニーズ・ウォンツ・インサイトの理解が鍵
- 顧客の声から事業のヒントを得る
- 数より信頼。焦らず積み重ねる姿勢
ニーズ・ウォンツ・インサイトの基本理解
-150x150.jpg)
集客や売上に悩む地方の小規模事業者にとって、本当に見るべきは「お客様の本音」。ニーズ・ウォンツ・インサイトの違いを理解し、たった1人の顧客の深い理解から、事業の方向性や強みが見えてきます。
(1)「ニーズ」と「ウォンツ」はどう違うのか?
上越妙高のような地方でお店や事業をしていると、「お客様が求めているものが分からない」「なかなか集客できない」と悩むことがあります。
それは、もしかしたら“ニーズ”と“ウォンツ”の違いをちゃんと整理できていないのかもしれません。
「ニーズ」は欲求の根っこの部分。
たとえば「自分に自信を持ちたい」「誰かに話を聞いてほしい」といった、本人さえも気づいていない感情が潜んでいます。
一方で、「ウォンツ」はお客様の“こうしたい”という希望。
「髪を切りたい」「爪をキレイにしたい」「相談に乗ってほしい」などです。
| 種類 | 意味 | 例 | ビジネス上の示唆 |
|---|---|---|---|
| ニーズ | 潜在的・根源的な欲求 | のどが渇いた | 顧客の本音や背景を捉える視点が必要 |
| ウォンツ | 顕在化した具体的な希望 | 炭酸水が飲みたい | 商品・サービスで応える(差別化が必要) |
(2)インサイトとは何か?
インサイトとは、「お客様が口に出さないけど、確実に抱えている本音」。
上越妙高にも、「毎日頑張ってるけど、どこか満たされない」そんな気持ちを持つ人が数多くいると思います。
たとえば、とあるサロンのお客様は「見た目を整えたい」と言いながらも、実は「仕事帰りにホッとできる場所がほしい」だけだったりする。
農業や小売業の現場でも、相談を受けると最初の話と本質的な課題が違っていた…といった事象はよくあります。
お客様の表情や話し方から、「この人が本当に求めているものは何か?」と感じ取る力。
それが、これからの時代の商売に求められる力です。
(3)顧客理解がドメインを再定義する
「うちはただのネイル屋だから」「野菜を売っている八百屋だよ」「町工場だからね」と経営者の方からよく耳にします。
しかしこのように自分のドメイン(事業領域)を狭めてしまうのはもったいないです。
あるサロンは、「オシャレを売る場所」から「心が整う時間を提供する空間」へとドメイン(事業領域)を転換しました。
するとお客様の見方も変わり、リピーターが自然と増えていったのです。
地方では、特定の技術や商品だけで勝負するよりも、「この人だからお願いしたい」と思われる関係性を築くことの方が、圧倒的に強い武器になりやすいと感じています。
1人の顧客理解がもたらす力
-150x150.jpg)
「まずは多くの人に知ってもらうべき」…そう思いがちですが、本当に大切なのは目の前の1人の顧客と深く向き合うこと。顧客理解の積み重ねが、信頼となり、やがて新たな顧客を連れてきてくれます。
(1)理想の「たった1人」と向き合う
「売上を増やすには、まずはたくさんの人に知ってもらわないと」と思いがちですが、それよりも大切なのは、目の前のたった1人の顧客を深く理解すること。
言い換えると、市場シェア拡大を狙うよりも、1人の顧客の中での“シェア”を広げていく、つまりファン化を目指す考え方です。
たとえば、毎月通ってくれるお客様。
会話の中にその人の価値観や生き方がにじみ出ています。
どんなことで喜んでくれるのか、何を気にしているのか。
その1人の声を、より丁寧に聞いてみましょう。
上越妙高にも「何十年もお付き合いしている常連さん」がいるお店は多いと思います。
その1人から得られるヒントは、新規集客の広告よりもよほど価値があります。
さらに、そうした“たった1人”の顧客像を深めていく過程で、視野を狭めないことも大切です。
たとえば、地元の商工会議所や異業種交流の場では、美容・建設・食品など多様な業種の人と接点が持てます。
そこでは、業界ごとの顧客ニーズの見え方、価値提供の仕方が全く異なります。
「自分とは違う業界の人が、どうやって顧客と向き合っているのか」を聞くだけでも、今まで気づけなかった“サービスの魅せ方”や“伝え方”が見えてくることもあります。
メンターのような存在が1人いることも心強いですが、情報源が1つだと無意識に偏りが出るもの。
だからこそ、情報は分散して持ち、時には業界外からの視点にヒントをもらうのが、地方で事業を続けるうえでとても重要です。
(2)小さな信頼がブランドになる
東京や大阪のような大きな市場ではないからこそ、信頼の積み重ねがビジネスの命綱になります。
「この人なら、安心して任せられる」と思ってもらえる関係性をどう築くかがカギです。
地方には、口コミが静かに、しかし確実に広がっていく特性があります。
「こないだあの店行ったら、すごく丁寧で気が利いてたよ」といった日常の会話が、次の顧客を生むこともあります。
看板よりも、SNSよりも、「あの人が勧めてた」一言が最強の宣伝になるのが、地方あるあるです。
看板やチラシ、SNSでの発信は集客に有効ですが、まずは心底うちの商品・サービスを愛してくれるお客様との出会いが最優先ではないでしょうか。
(3)顧客の無意識を“言語化”する
とあるお客様が、「家に帰って、ふとネイルを見たら元気が出た」と言ったそうです。
本人も気づいていなかったその一言に、実は大きなヒントがあります。
「気分が沈んだとき、ふと元気を取り戻せる存在」――これが自分のサービスの価値なんだと気づいたとき、メッセージの発信の仕方が変わります。
地方では、ただ“安さ”や“技術力”を押し出すだけでは伝わりにくいかもしれません。
むしろ、生活の中にそっと寄り添う存在であることを丁寧に伝えることが、選ばれる理由になります。
新規顧客は「伝え方」で変わる
-150x150.jpg)
新規顧客を増やしたい時こそ、見直すべきは「伝え方」。サービスの魅力が伝わらないのは、価値がないからではなく、伝え方にズレがあるのかもしれません。
(1)売り込むより“気づかせる”伝え方
「うちはいいサービス(製品・商品)をしているのに、なかなか伝わらない」と悩む方は多いです。
ですが、それは“何を売っているか”ではなく、“どう伝えているか”が課題かもしれません。
たとえばネイルサロンであれば「完全予約制でゆっくり過ごせます」「人目を気にせず相談できます」など、地域の人たちが日常で抱えている小さな悩みに寄り添う言葉を使うだけで、反応は大きく変わります。
紙媒体のチラシもInstagramも、地元の言葉で語りかけることが大事なのではないでしょうか。
(2)お客様の声をそのまま使う
地方のお客様は、直球の広告に慣れていません。
しかし、誰かのリアルな体験談には敏感に反応します。
「仕事帰りにホッとできる時間です」「誰にも言えなかったことを話せました」など、お客様の声をそのまま紹介するだけで、共感が生まれます。
“自分のためのお店かも”と思ってもらえるような、リアルな言葉で発信しましょう。
(3)「売上」より「信頼」が先に来る
つい数字ばかり追いがちになりますが、地方ビジネスの本質は“人との信頼”です。
目の前の1人に本気で向き合い、その人に心から満足してもらえるか。
そこから生まれる信頼の輪が、少しずつ周りに広がっていきます。
焦らずに、じっくりと。その積み重ねが、新しいお客様を連れてきてくれます。
もちろん、個人事業主でも経営者でも生活がかかっているからこそ「今月の売上」は大切です。
しかし、目先の数字に振り回されて、無理な値下げや自商品・サービスを大きく見せるような広告を打ってしまうと、本来の価値や方向性がブレてしまい、かえって目的・目標から遠ざかってしまう可能性が高まります。
事業はマラソンです。
創業からしばらくは、売上が少なくて当然。
むしろ“顧客の声を蓄積し、改善し、信頼を育てる時間”と考えたほうがよいのではないでしょうか。
あるタイミングで、それまで地道に積み上げてきた信頼が“加速装置”のように働き、「あれ、最近やたら紹介が増えたな」という瞬間が必ず来ます。
その時のために、“焦らず、でも止まらず”を心がけましょう。
“たった1人の顧客”に向き合うことが、道を開く
事業がうまくいかないとき、視野が広がりすぎて迷ってしまうことがあります。
そんな時こそ原点回帰。
目の前の1人の顧客を深く理解し、伝え方を工夫し、信頼を丁寧に積み重ねることで、自然と新たな出会いが生まれていきます。