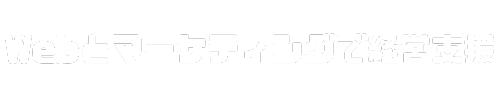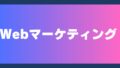上越・妙高エリアのモノやサービスの品質は、非常に素晴らしいです。特に上越市は他自治体よりも二次産業比率が高く、製造業や建設業の方々が産業基盤を支えてくれています。
日本全国に目を向けても、近年ではインバウンドが急増し、多くの外国人観光客が日本の精緻なモノづくりや、おもてなしにあふれた接客サービスに感動しています。
しかし一方で、「いいモノをつくれば売れる」という考え方が通用しにくい時代になってきました。
本記事では、資金や人手に限りがある中小企業が、“自社らしさ”を活かしながら、無理なく始められるマーケティングの考え方と実践方法を、わかりやすく解説します。
本記事のポイント
- 「いいモノをつくれば売れる」は通用しにくい時代
- 中小企業は“自社らしさ”が最強の武器になります
- 無理なく始められるマーケティング思考を紹介します
なぜ今、マーケティングが必要なのか?
-150x150.jpg)
時代の変化とともに、売れる仕組みづくりの重要性が高まっています。
(1)「いいモノをつくれば売れる」は本当か?
高品質な製品を長年作り続けて、大手企業からの注文に応えてきた中小企業も多いかと思います。しかし、原材料の高騰や物価の先行き不透明感など、外部環境は大きく変化しています。
その中で、大手企業からの価格交渉も厳しくなり、値上げは難しく、利益はますます圧迫される状況です。こうした中、「いいモノをつくれば売れる」という信念が、現代では通用しにくくなってきているのが実情です。
(2)マーケティングは「広告」でも「値引き」でもない
「マーケティング」と聞くと、「チラシを配ること」や「SNSで拡散すること」と思われる方も多いようです。
しかし、本来のマーケティングとは「誰に・何を・どう届けるか」を体系的に考える一連の活動です。「売上を上げる」ための手段ではなく、「売れる仕組み」をつくるための土台なのです。
(3)中小企業にこそ、マーケティング視点が必要な理由
資本力で劣る中小企業にとって、マーケティングとは「勝てる土俵を選ぶ戦略」そのものです。大手企業と同じ土俵で勝負しても、資金・設備・人材など経営資源では勝ち目がありません。
だからこそ、“当社らしさ”という強みを「誰のために、どう活かすか」を考えるマーケティング視点が重要です。
「自社らしさ」を武器にするマーケティング
-150x150.jpg)
限られた資源でも、“自社らしさ”を活かせば選ばれる理由になります。
(1)強みを「相手視点」で捉え直す
顧客にとっての価値は何かを考えることが大切です。
たとえば、「創業60年のモノづくりの技術力」や「熟練技能者のスキル」は確かに大きな強みです。
しかし、その価値は本当に伝わっているでしょうか?技術や品質を“相手の困りごと”と結びつけてこそ、意味を持ちます。
「うちはこれが得意」ではなく、「誰にとって、どんな意味があるか」を言語化することが第一歩です。
(2)「ニッチな市場」こそ、中小企業の主戦場
確実な売上が見込める大きな市場には、すでに大手企業が存在しています。一方で、まだ誰も注目していない小さなニーズを見つけることが鍵になります。
必ずしも新しい製品をつくる必要はありません。提供方法(たとえば定期購買・サブスク)や体験価値(工場見学、農作業体験など)を変えるだけでも十分かもしれません。「こんな用途があったのか」と思われるような提案が、差別化となり価格競争を避ける武器になります。
(3)ブランド=会社の“らしさ”を伝える力
「社長が誰か」「どんな想いで事業を行っているか」は、大手には真似しづらい中小企業の魅力です。
たとえば家族経営の温かさ、細やかな対応、小ロットへの柔軟な対応など、自社の“らしさ”をブランドとして伝えることで、ファンが生まれやすくなります。
製品の機能だけでなく、「誰が、なぜ、どう届けているのか」というストーリーが、顧客の共感を呼ぶ時代です。
実践!マーケティング的思考の導入法
-150x150.jpg)
マーケティングは、小さく始めて現場に根づかせることが大切です。
(1)「理想の顧客像」を明確にする
すべての人に売ろうとするのではなく、「自社製品の価値を正しく理解してくれる人」は誰かを定めましょう。仮でも構いません。
たとえば、「品質にこだわる中小メーカー」や「スピードより精度を求める研究開発部門」など、具体的な顧客像を描くことで、メッセージや提案のズレが減ります。
ゼロから考えるのが難しい場合は、既存顧客の中から「理想の顧客」を見つけるのも有効です。
(2)小さく試して、反応を見る
最初から大きな市場に出る必要はありません。まずは「理想の顧客像」に、自社の強みを活かした製品を届けてみましょう。
「何が響いたのか」「なぜ選ばれたのか」あるいは「どこが響かなかったのか」など、顧客の声を丁寧に拾い、改善・改良を重ねる。この仮説検証のプロセスが、「売れる仕組み」づくりの核心です。
(3)「売れる仕組み」をチームでつくる
製造・営業・経理など、複数の部門がある企業では、仕組み化を意識して取り組むことをおすすめします。
多様な視点や価値観を持つメンバーが関わることで、経営者一人で考えるよりも、より“面白いモノ”が生まれる可能性が高くなります。もちろんそれは顧客にとって“面白い”という意味です。
組織的に取り組むことで、他社には真似できない独自性が生まれ、持続的な成長につながります。
マーケティングはあくまで「道具」です
「地域に貢献したい」「親の代から受け継いだ会社をさらに成長させたい」――
その想いは、誰よりも経営者自身が強く抱いていらっしゃるはずです。
マーケティングは、その想いを形にするための“考え方の道具”にすぎません。
売上を上げるためではなく、「売れる仕組み」をつくり、会社の未来を描く力として、まずは一歩を踏み出してみませんか。