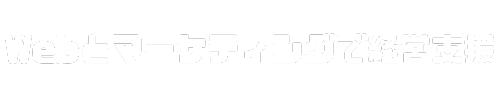「SNS?Web?DX?…とにかく苦手だし、専門の業者に任せればいいでしょ」
上越商工会議所や妙高で経営者の方が集まる場でよく聞きます。
確かに、デザインや技術はプロに任せた方が効率的です。
しかし自社で何も触れず、検証すべき数字もわからない状態では、改善のしようがなく“丸投げしたまま”で止まってしまいます。
場合によっては悪徳業者に謎のメンテナンス料金だけ吸い上げられ、デジタルが嫌いになるかもしれません。
経営者自身がほんの少しでも「デジタル」に触れる必要がありますが、今回は「なぜ丸投げがうまくいかないのか」「経営者がやるべき最小限のこと」「組織としてデジタルと向き合う方法」についてお伝えします。
本記事のポイント
- 丸投げではWebは“経営資産”にならない
- 経営者の関与がデジタル活用の出発点
- 社内で運用・発信できる体制づくりが鍵
なぜ“丸投げ”はうまくいかないのか?
-150x150.jpg)
Webを外注しても、自社で扱えず理解も薄ければ改善はできず、社内での定着も難しいです。
(1)丸投げ=ブラックボックス化するWeb
外注して立派なWebサイトができたのに「内容を自分で変えられない」「アクセス数が見られない」では、改善も戦略も立てようがありません。
リアルで言えば、立派な店舗を構えたのに、誰が来ているのかも、何が売れているのかも分からない状態と同じです。
Webサイトのデザインが高品質なのは素晴らしいことですが、それだけでは経営資源を“消費”して終わってしまいます。
本来は、アクセス解析や情報の更新を通じて、Webも事業の“資産”として機能させるべきなのです。
(2)“わからない”が意思決定の妨げになる
「なんとなく任せている」「報告は来るけど理解できない」状態では、経営判断ができず、任せているはずの業者に依存する構造になります。
これは、思考停止と同じです。
数字の意味や動線の構造を理解しないままでは、判断軸が育たず、改善のタイミングも見逃してしまいます。
(3)経営者が無関心なことは、社内に根づかない
デジタルを「自分の仕事ではない」と考えていると、社員にも伝播します。結果、誰も主体的に扱えないまま、“デジタル化ごっこ”で終わってしまいます。
せっかくのWebへの投資も無駄遣いをしてしまう事になりかねません。
経営者が「ほんの少し」やるべきこと
-150x150.jpg)
苦手でも、経営者が少し踏み出すだけで、デジタルは経営の強力な武器に変わります。
(1)まずは“自分で投稿”してみる
「え…投稿?何を?」と抵抗感を持たれるのは自然な感情かもしれません。
それでもSNS(Instagram、YouTubeショート等)でたった一つ投稿してみることから始めてみませんか?
SNSの投稿方法については身近な詳しい方(若手従業員や信頼できる専門家)に聞きながらでいいと思います。
経営者の方はWebの専門家ではなく、経営のプロですから。
実際に投稿してみて、Webのアクセス数を自分で見てみる。
それだけで、数字や反応に対する感度が上がり、改善の視点が生まれます。
(2)構造を理解する=損をしない経営判断
「どういう仕組みで見られているのか」「どこを改善すべきか」といったWebやSNSの構造を、ざっくりでも理解するだけで、業者との会話が一方通行ではなくなります。
丸投げではなく“連携”に変わり、結果として無駄な費用やズレた施策を避けられるようになります。
最低限、以下のような質問を投げかけてくる外注業者であれば、戦略的な連携が可能です。
これらはマーケティング視点を持っていれば自然と出てくる質問です。
- 「サイト構築の目的は何ですか?」
- 「ターゲット顧客はどのような方ですか?」
- 「その顧客はどのような課題やニーズを持っていますか?」
- 「その顧客に最終的にどんな行動を取ってほしいですか?」
- 「自社の製品・商品の強みは何ですか?」
このような対話を通じて、初めて“成果に向かうWeb施策”が設計されていきます。
逆に、これらの問いが一切ない業者は、見た目重視や技術偏重で、本質的な価値提供にはつながりにくい可能性があります。
↓↓↓マーケティングとは?↓↓↓
(3)目的を持つと、使い方が変わる
「とりあえずやってるSNS」ではなく、「自社製品の売上構成比を上げる」という目的を明確にすると、デジタルの使い方が戦略的になります。
目的が明確になれば、「何を・誰に・どのように」発信すべきかが定まり、施策がブレなくなります。
最終的には“組織”で動かす
-150x150.jpg)
経営者が関わるだけでなく、社内に仕組みと意識を根づかせていくことが、持続的なデジタル活用の鍵です。
(1)編集できる仕組みを社内に残す
業者に任せる場合でも、「自社で編集できる環境」や「社内で運用可能な体制」を持っておくことは不可欠です。
外注したまま放置すると、修正や改善のたびにコストがかかり、スピード感も失われます。
誰か一人に依存せず、複数人が関われる体制をつくることで、属人化を防ぎ、継続的な発信や改善が可能になります。
これは、Webを一時的な販促ツールではなく、長期的な経営資産に変えるための重要な土台です。
(2)“使える人材”ではなく“育てる意識”
“使える人材”を外から探すのではなく、今いるメンバーと一緒に学ぶ姿勢が大切です。
初期は信頼できる専門家の力を借りるのも有効ですが、最も重要なのは経営者自身が関心を持ち、行動すること。
その姿勢が従業員の意識に火をつけ、社内にデジタルへの前向きな空気を生み出します。
(3)全社で“情報発信できる会社”へ
WebやSNSは一部の担当者だけで動かすものではなく、現場や営業を含む全社的な関与が重要です。
組織全体が情報発信に前向きな体質になることで、経営戦略と連動した効果的なWeb活用が可能になります。
今後の時代においては、情報を自ら発信できる企業であることが競争力の源となります。
デジタルは経営戦略の一部
「よくわからないから丸投げ」は楽ですが、成長を止める大きな要因になりかねません。
売上拡大に必要なブランド力や信頼構築には、デジタルの活用が不可欠です。
経営者がすべてを理解する必要はありませんが、無関心でいては社内にも根づきません。
まずは自ら一歩踏み出し、社内に“触れる人”を増やしていくことで、組織全体のデジタル活用が進みます。